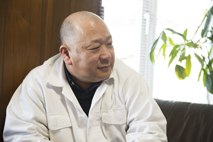Back number
過去に紹介した生産者
- 第24号
- 第23号
- 第22号
- 第21号
- 第20号
- 第19号
- 第18号
- 第17号
- 第16号
- 第15号
- 第14号
- 第13号
- 第12号
- 第11号
- 第10号
- 第9号
- 第8号
- 第7号
- 第6号
- 第5号
- 第4号
- 第3号
- 第2号
- 創刊号
第24号( 2019年10月 )

大淀町 嘉兵衛本舗の
天日干し番茶
大淀町の小さな村の中で「かへえさん」と親しまれた森本嘉兵衛さんがお茶づくりを始めたのは、今からおよそ170年前のこと。次号の主役は、六代目であるお父さまからお茶の仕事を受け継ぐ為に奮闘する三人の娘さんたちの姿を追う。お届けするのは、吉野の山里で育てられた天日干しの「嘉兵衛番茶」。土壌を活かした農法と昔ながらのほうじ加工を忠実に守り続け、日々の暮らしに寄り添う、どこか懐かしい味と日向の香りをお届けします。
第23号( 2019年8月 )

木本芳樹さんが育てる
軟白ずいき
「軟白ずいき」はエグみの少ない赤茎の唐芋で成長過程の草丈を新聞紙で覆って遮光。それを何度も繰り返し、真っ白な茎のずいきを作り出します。その稀少性や独特の食感、そして出汁をよく吸う食材なので、主に料亭や割烹など和食で季節感を出すために珍重された高級食材。そのため、なかなか家庭の食卓には登場しないので、知らない人も多いはず。奈良県では奈良市西狭川町が主な産地でした。しかし、手間とコストが合わず、今は作る人がほとんど居なくなってしまい、稀少性の高い食材です。食材を作る人が減ったことで、それに紐付いた歴史や文化を遡ることも難しくなり、取材も難航を極めました。完全になくなってしまう前に!と立ち上がった木本さんが今回の主役。歴史やストーリーを紐解くことが難しかったこともあり、今回は木本さんが育てたその「軟白ずいき」という食材がどんなものなのか、家庭でどのように食べられていたのか、そして料理人がどのように究極の一皿に仕上げたのか・・・。
第22号( 2019年6月 )

五條市
益田農園のオオモノトウモロコシ
一株に2、3つのトウモロコシが出来ますが、1本に栄養、そして甘みを集中させるためにヤングコーンのタイミングで残りを剪定します。とはいえ、1万本以上のトウモロコシが収穫できるから驚いていると、「まだまだ少ないねん。もっと増やしたい」と、益田さん。「他にもキャベツは12万個、玉ねぎは40万個、柿は…よくわからん。それでも決して大規模な農家ちゃうし」。素人的にはよく分からない領域だ。7月中旬の収穫に向けて、霜や台風が来ない事を願うばかりだ。
第21号( 2019年4月 )

『山口農園』の
有機野菜
私たちはこの号を通して「有機農業が良い、慣行農業が悪い」ということを言いたいわけではありません。農業に間違いはなく、どれもが正解。全ては「選択」だと思います。今回の主役である『山口農園』を取り上げたのも、有機農業を選択したその理由にありました。約10ヘクタールにハウス165棟という広い圃場でたくさんの人を雇用し、有機JAS認定の農業法人にも関わらず生産効率を追求。経営手法を駆使し、利益重視、ビジネスとして有機農業に取り組み成功した農業生産法人。それが私たちの思い描いていた『山口農園』のイメージでした。 しかし、取材を重ねるにつれ、それは表面的な見方であると同時に、本質はそこではないことに気づかされました。「健康、安全と安心、美味しいも当然意識しています。けれど、あくまで有機農業は選択であり手段です」と社長の山口貴義さんはおっしゃいました。本質的な目的は「地域、そして環境を守ること」、「未来をつくること」。あくまでも「今、この地球に生きる自分たちが環境負荷の少ない農業を推進し、有機農業に携わる人がきちんと稼ぐことが出来る仕組みをつくること」それが『山口農園』の目指す有機農業だったのです。 取材の最後に「生産者(つくるひと)として消費者(食べるひと)に期待することは何ですか?」の問いに「皆さんにも有機野菜を購入するという選択で、地球の環境を守ることに1票を投じてほしい」と山口さん。私たちの未来は、私たちの選択によって変わります。今月号では、その根っこにある『山口農園』の有機農業のあり方を特集しました。
第20号( 2019年2月 )

奈良県在来の大豆
大鉄砲
縄文時代に日本に伝わったとされる「大豆」。納豆・醤油・味噌・きな粉など、和食とはきってもきれない縁をもつ。「畑の肉」とよばれるほど栄養価が高く、3大栄養素のうちのタンパク質と脂質をもっている。田んぼのあぜ道で栽培されており、不足する炭水化物をコメで補うことができる。大豆は日本人の食卓に欠かせないものだった。しかし、米の収穫時期が早くなったことや安い外国産が入ってきたことにより、大豆から他の作物へと切り替えざるをえなかった。さらに、平野部が少ない奈良県ではまとまった量の県産大豆を作る農家がほとんどいなかった。今回の主役である、創立70年の大豆加工会社『(有)三木食品工業』の専務近藤さんはシェフェスタをきっかけに県産大豆を使った豆腐作りを一からスタートした。幼い頃、野球にうちこんだことで、夢の実現に向けて努力することを惜しまない近藤さん。そんな彼の情熱に共感する人が次々につながり、やがてそれがひとつのチームとなる。奈良県内の豆腐屋から戦前より大鉄砲という奈良の在来品種があることを知らされた。消滅しかけていた大鉄砲を育てる農家を探す中で出会った西野さん、そして田原本町で農業を営む鎌田さんが生産者となった。岐阜県から届いた大鉄砲は既に芽を出し、近藤さんの夢が形なる日がきた。「豆腐のルーツを持つ奈良県で、県産を使った豆腐を作りたい」。今、彼はかつて甲子園のグラウンドで1球に込めた情熱を一丁の豆腐に注ぐ。
第19号( 2018年12月 )

大和伝統野菜
八条水菜
八条水菜が育てられ場所は奈良市八条。奈良市の中心部から車で10分程度の平野部に位置するこの土地で代々、種を自家採種し、紡いできたこの水菜。「鍋にしたら、ほんまに美味いねん。この水菜を食べたら、他の水菜は食えへん」これは取材中にお父さんたちが何度も口にした言葉。そして「この地に生まれたら、水菜を作るのは当たり前のこと。けど、どの家の息子たちも都会に出てしまって一緒に住んどらん。だから、俺らの代で終わるかもな」と、少々悲しそうに語るお父さんたち。どの農家も同じような状況なのかもしれませんが、美味いこの水菜の種が途絶えることだけは避けたいと思う編集部。この水菜のバトンはここで途絶えるのか、それとも新たな光を届けることができるのか。我々、編集部にも何か託されたような気がする。
第18号( 2018年10月 )

西吉野町平井農園の
富有柿
『奈良食べる通信』10月号は奈良県が誇る柿。その一大産地ともいえる五條市西吉野町で梨と柿を育てる『平井農園』。"僕たちは柿の木の恩恵を受けているんだよ"と平井満男さん。柿の木をまるで家族のことのように語る満男さんと久美さんは明るく笑顔が絶えない。どんな人でも家族のように受け入れてくれる二人の周りにはたくさんの人の笑顔がある。満男さんは”自分はもともとは頑固者で、周りとの交流はほとんどなかった”と語るが、社交的な久美さんとの出会いにより、それが変わり始める。"はじまりの奈良"を契機に奈良県内の飲食店での流通など、新たな人たちとのつながりや販路ができた。子どものない二人の願いは、"この柿の木を後世に残していきたい"ということ。そのため、新規就農者の吉岡崇さんを受け入れた。二人が我が子のように育ててきた柿の木は繋がりという大切な実も実らせたのだ。
第17号( 2018年8月 )

天理市の出垣滋さんが育てる
道安宝珠喜
『奈良食べる通信』8月号にてお送りするのは、天理市山田町で出垣滋さんが育てる食用ほおずき「道安宝珠喜(どうあんほおずき)」。観賞用のほおずきは馴染みがあるかもしれませんが、食用ほおずきはまだまだ流通が少なく、食べた事がない、という方もおられるのではないでしょうか?ビタミンA・Cや鉄分が多く含まれており、ヨーロッパではスーパーフードとして家庭でも親しまれています。「道安宝珠喜(どうあんほおずき)」の名前の由来は戦国時代、この山田地区を治めていた山田道安からとったもの。普段は、料亭やレストラン、限られた売場にしか出荷していないという出垣さんの「道安宝珠喜」。トマトのような、梨のような、甘酸っぱく爽やかなヨーグルトのような、いつまでも食べ続けたくなる味。
第16号( 2018年6月 )

十津川村・上湯川地区の
なめこ
『奈良食べる通信』6月号で取り上げるのは日本で一番大きな村、十津川村でも奥の奥、まさに陸の孤島と呼ぶにふさわしい上湯川地区。そんな場所で作られている「なめこ」をご紹介しています。人口減少が激しい辺境の地で雇用を生み出し、地域にとって欠かせない産業となっている「上湯川きのこ生産組合」のきのこ栽培。効率化や生産性を第一とするのではなく、品質の高い商品(きのこ)を作り出すため、あえて人間の手仕事を残してきました。その結果、遠方からの注文も絶えない美味しいきのこができました。百聞は一見に如かず、一度食べて見てください。そうすれば、今まで食べてきた「なめこ」の概念が覆るはず。
第15号( 2018年4月 )

家族の絆を紡ぐ
さかもと養鶏の
白鳳卵
第14号( 2018年2月 )

山添村で
下川麻紀さんが育てる
れんこん
第13号( 2017年12月 )

「食べやんとわからへんから」
ファーム曽楽の
寒熟ほうれん草
曽爾村でほうれん草は年間5〜6作、つまり一年中つくられている。そのなかでも、「大和寒熟ほうれん草」は毎年12月下旬〜2月下旬までの季節限定出荷のブランド品だ。最も糖度が高くなるのは、例年1月20日前後〜2月初旬。寒さで糖度が上がっても、気温が5度以上になると糖度が下がってしまうので、ハウスの風通しの調整が必要となる。非常に繊細な野菜だ。2月末を過ぎたら、一般的なほうれん草として出荷される。「食べてみやんとわからへんから」。曽爾村のお父ちゃんたちの言葉が強く印象に残る。一般的なほうれん草の糖度は5〜6度、それに比べて大和寒熟ほうれん草の糖度は10度前後、最も高いので15度、つまりイチゴ以上の甘さを誇る。その分手間暇がかかるわけだが、実際店頭に並べば、一般的なほうれん草と金額の差はほとんどつかない。それでも「しぶとうやってきた」そう語るお父ちゃんらを追いかける。
第12号( 2017年10月 )

明日香グリーンファームが
新たな農業を創ろうとする
明日香きくらげ
五條市相谷町の自然豊かな場所で、約3500坪もの圃場を持つ「アスカグリーンファーム」。ここでは、純国産の黒きくらげと白きくらげの2種類をメインに、大和野菜も育てている。前述した純国産は、国産とは意味が異なる。私たち編集部も取材するまで知らなかったのだが、きくらげ市場の約97%が中国産。その他3%が国産で、その中でもわずか1%にも満たないものが純国産と言われるもの。原材料もすべて国産のものを使用した上で、かつ国内で育てられた正真正銘の日本国産きくらげのこと。ここ「アスカグリーンファーム」では、安心安全な食材作りはもちろんのことながら、生産性の向上や六次産業化などにより、農業の現場を抱える問題を解決することで、農業の変革までを視野に入れている。また、一般的な黒きくらげだけでなく、希少な白きくらげの栽培にも成功。その確率、なんと10000分の1。彼らのその一筋の光を追いかける。
第11号( 2017年8月 )

「好きやから百姓やってます」
葛城市で寺田昌史さんが育てる
ハーブと無花果
農家の息子として生まれ、「好きやから百姓やってます」のキャッチフレーズでお馴染みの寺田農園・農園長の寺田昌史さん。ハウスを訪れると、中から聞こえるのは陽気な歌声とギター音。その正体は、“歌うたい”と言いたいところだが、ばりばりの農家人。23歳という若さで莫大な資金を投資、選んだのは約3300坪にもなる敷地で水耕栽培というやり方だった。バジル、ディル、チャービルなどのハーブをメインに、無花果、米、奈良のブランドいちご古都華などを育てている。その覚悟の裏側には、死にたいとまで思った農業に対する葛藤と苦悩があった。彼のそれでも百姓であり続ける想いを追いかけました。
第10号( 2017年6月 )

大和の伝統野菜のひとつ
丸三出荷組合の中西さんたちが作る
大和丸なす
大和丸なすは、奈良県が認定する「大和の伝統野菜」のひとつ。直径約10センチと大きく丸い。濃い紫で、色つやがよく、皮にはピンと張りがある。肉質は緻密で、煮崩れしにくいのが特徴。煮物や天ぷらなど、加熱するとトロッとしたやわらかさも楽しめる。市場での評価も高く、東京や大阪などの高級料亭が好んで使う高級野菜でもある。大和郡山市平和地区を中心に、9軒の農家で構成する『丸三出荷組合』は、伝統を受け継ぎ、大和丸なすの生産と出荷を行なっている。その中でも、今回の主役は中西拓彦さん。義父の農場を受け継ぎ、大和丸なすのほか、イチジクやイチゴなどを栽培。レストランのシェフと交流し、イベントや勉強会にも熱心に参加するなど、農業に楽しさを見つけ、より良い作物を育てようと奮闘する姿を追いかけた。
第9号( 2017年4月 )

金井畜産が挑戦する奈良のブランド牛
まほろば赤牛
奈良には『大和牛』というブランド牛がある。この良質な黒毛和牛は霜降りもよく、多くのシェフや美食家から高い評価を得ているが、生産量も少なく、高価なものとして口に入りづらくなっている。その『大和牛』も飼育している金井畜産では、食のヘルシー志向や熟成肉のブームなどを受けて、赤身と脂のバランスがよい赤牛の導入を始めた。従来の霜降り礼賛ではない、しっかりと旨味のある奈良の新たなブランド牛を目指している。良質な『大和牛』を育てるノウハウを生かし、水と空気が美しい宇陀の地で育てる『まほろば赤牛』の魅力とは? また、同社社長の金井啓作さんは、新潟出身ながら、10代から奈良県内で、食肉の卸しから畜産へと、肉に関わり続けてきた。金井さんの生き様と、奈良の畜産現場と食肉流通の変遷も追いかける。
第8号( 2017年2月 )

下北山村でしか採れない大和伝統野菜
下北春まな
極寒の12月半ば、2日間という泊まり込み取材で向かった先は下北山村。事務所がある生駒から、車で走ること約3時間。下北山村は、奈良県の南端、実に山深い場所にある。この村で、明治時代から作り続けられているのが、下北春まなだ。農緑色で丸みがかかった葉は、肉厚で大きいのが特徴。自家栽培、自家採種、自家消費がメインであり、かつ寒さ厳しい真冬にしか採れないため、村外に流通することがほとんどない、幻の野菜と言われている。おひたしや鍋にしてもおいしいが、村では、保存食として漬物にすることが多い。中でも、温かいご飯を包んで食べる「めはり寿司」が、郷土料理として長く親しまれている。一時期は、生産者も減り、絶滅の危機に瀕していたが、漬物の商品化、粉末を利用した商品開発などを通じて、村の特産品にしようと取り組んできた。高齢化、過疎化が進む村ながら、地の作物を通して、村を元気にしようとがんばる人たちを追いました。
第7号( 2016年12月 )

明日香村で樽井一樹さんが作る
古代米
古代米とは、「古代の野生稲の特徴を受け継いだ品種」などと説明されます。赤、黒、緑など、色に特徴があるものが多く、赤米に含まれるタンニン、黒米のアントシアニン、緑米のクロロフィルなどの色素が健康に良いとして注目を集めています。明日香村では、特産品として、赤、黒、緑の古代米を栽培していますが、「たるたる農園」の樽井一樹さんは、自然農法でこれら3種の古代米に加え、香米と御神米を栽培しています。12月号は、5種類の古代米をブレンドしてお届け。脱サラから自然農法による農業へと人生の舵を取った樽井さんは、地域の生産者と共に「明日香ビオマルシェ」を開設するなど、積極的に活動しています。自然と調和しながら野菜や米を育てる自然農法を通して、樽井さんが見据えるものとは何か、存分に語っていただきました。
第6号( 2016年10月 )

大宇陀で黒川本家が作る
吉野本葛
創業400年を超える吉野葛の老舗、黒川本家。その歴史は、江戸時代初期、初代の黒川道安が吉野の葛根を使って葛粉を作り、京の朝廷に献上したのが始まりと伝えられています。その後、大和松山藩領(現在の宇陀市大宇陀地区)を本拠とし、以来、製法を一切変えず、現在まで受け継がれてきました。吉野葛作りは、厳寒の冬に行なわれます。山から掘った葛根を砕き、清廉な井戸水に何度もさらし、純白になるまで清めていく。この製法を「吉野晒し」と言います。 吉野葛は、和菓子に用いられる他、料理では汁のとろみつけに使われます。しかし、片栗粉やコーンスターチに比べると高価であり、扱いにくく、残念ながら一般家庭では使われなくなっています。400年という長き歴史を歩んできた吉野葛と黒川本家の歴史を紐解き、秘められた魅力を多面的にご紹介しました。 今回は、特集で紹介した黒川本家の「吉野本葛」(190g)お送りしました。また、その本葛を使った葛餅、葛豆腐、葛ぜんざい、葛湯(4種)を増量商品としてご案内しました。
第5号( 2016年8月 )

「泉澤農園」泉澤ファミリーが育てた
ばあく豚
日本全国にある銘柄豚は、およそ300といいます。奈良県が認定する銘柄豚にヤマトポークがありますが、より高い意識とこだわりを持って飼育しているのが、泉澤農園の『ばあく豚』です。県南部の五條市、見晴らしの良い葛城山麓に豚舎を構えて30年以上。黒豚に茶色の豚を掛け合わせる独自の交配により、霜降りの豚肉を生み出しました。また、自家配合飼料に、大麦や小麦を多くするほか、パンくずやビール麦の残渣利用など、リサイクル意識も高く、数年前からは小麦の栽培も始め、地域による循環型農業への道を歩んでいます。 今回は、ロース、バラ、モモのスライスをセットでお送りしました。泉澤農園で育てた豚は、『農家レストラン ばあく』にて、無添加のソーセージやベーコンなどに加工されます。こちらは、増量商品としてご案内しました。
第4号( 2016年6月 )

「健一自然農園」伊川健一さんの
大和茶
大和茶は、西暦806年、弘法大師(空海)が唐から茶の種を持ち帰り、現在の宇陀市にある佛隆寺で播種したのが起源とされています。その後、大和高原を中心に栽培が広がり、良質な茶葉を栽培してきましたが、近年は、ブランド力の低下やお茶離れなどから低迷が続いています。廃業によって放棄される茶畑が増える中で、伊川健一さんは、自然に寄り添った農法による茶葉の栽培を実践。また、喫茶店運営や商品開発といった多角的な活動に加え、周辺住民や新規就農者と共に自然農法を広め、耕作放棄地の復元にも力を入れています。 大和茶ブランドの復活と、持続可能な社会の実現を目指して、精力的に活動する伊川さんのストーリーをお伝えし、都祁(田原)、山添、宇陀、それぞれの栽培地域の個性を生かした3種類のお茶をお届けしました。
第3号( 2016年4月 )

「新鮮しいたけおかもと」岡本隆志さんの
原木しいたけ
「木を生かし、木と生きる」。山林に囲まれた吉野という土地で、祖母が始めた原木しいたけ栽培。その生業は両親へ、そして、三代目となる岡本隆志さん、まどかさん夫妻へと受け継がれた。ナラやクヌギの木で菌を育てる原木しいたけは、味、香り、歯ごたえが優れています。さらに、ハウスの利便性に頼るだけでなく、できるだけ自然に近い環境で育てることにより、菌本来の力が引きだされるといいます。10年から20年かけて育った山の木を生かし、その生命力を“しいたけ”という食べものに変えていく。原木によるしいたけ栽培は、山の恵みを生かす日本古来の栽培法。まさに、自然と共生するモノづくりを大切に受け継ぐ岡本ファミリーの奮闘をお伝えします。
第2号( 2016年2月 )

「雅CHICKFARM」中家雅人さんの
大和肉鶏
戦前、京阪神で上質な鶏肉として愛された奈良の『大和かしわ』。しかし、ブロイラーの普及と反比例して、その生産量は減少の一途をたどりました。今からおよそ40年前、幻となった味を復活させるべく、8年の歳月をかけて開発した地鶏が『大和肉鶏』です。通常、ブロイラーが60日ほどで出荷されるのに対し、大和肉鶏は120~140日かけて育てています。飼料にこだわり、目をかけ手間をかけ、長く健康に育てられた大和肉鶏は、しっかりとした歯ごたえと、噛むほどにあふれる濃い旨味が特徴です。中家雅人さんは、自然環境に恵まれた柳生の里で、愛情を注ぎながら大和肉鶏を育てています。正直、高価な食材です。ただ、この機会に少しでも味わっていただければ、生産者の想いがこもった鶏肉の本当の価値をおわかりいただけると思います。
創刊号( 2015年12月 )

「グリーンワーム21」柏木英俊さんの
宇陀金ごぼう
金粉をまぶしたように、表面がキラキラと輝くごぼう。輝きの正体は、土壌に含まれる雲母(うんも)です。宇陀の土地は、昔ながらに雲母を多く含むため、この地で育つごぼうの美しさから名前が付けられました。ごぼうの中でも、香りがよく、肉質がやわらかいのが特徴で、太いほうがやわらかい食感が楽しめます。11月から収穫が始まるが、寒い時期の収穫作業は大変なもの。SNSでは、その収穫作業の様子なども配信していきます。 宇陀金ごぼうは、『大和の伝統野菜』のひとつに認定されており、その姿から、縁起物としても珍重されています。季節柄、お節料理に用いられることも多いので、12月の創刊号でお送りすることになりました。ぜひ、正月の食卓に奈良の縁起物を加えてください。